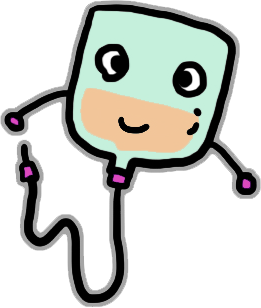
神経脊髄炎(NMOSD)は再発を繰り返すのが特徴です。再発の程度も大きく、1回の再発で歩けなくなったり目が見えなくなったりすることもあります。このようなことを繰り返すと障害が増えていってしまうため、NMOSDでは診断されたらすぐ、再発を予防する治療を始めます。
NMOSDの再発予防薬には、大きく分けて、経口の免疫抑制薬と生物学的製剤があります。ここでは生物学的製剤のラブリズマブ(ユルトミリス®)について解説しています。8週間に1回の点滴薬です。日本では2023年に承認されました。
全体的なこと
NMOSDは血液中のアクアポリン4抗体(AQP4抗体)が、アストロサイトの足突起にあるアクアポリン4を攻撃することによって起こります。AQP4抗体がアストロサイトを攻撃する際には「補体」と呼ばれるタンパク質が活性化することが分かっています。
ユルトミリス®はこの補体の成分の1つ「C5」に結合することで、その活性化を阻害します。そうすることでNMOSDの再発を抑えることができると考えられています。
ユルトミリス®は点滴薬で、初回、2回目は初回から2週間後、以降8週間ごとに治療を受けます。1回の点滴所要時間は体重によって異なり、25〜55分ほどです。基本的には初回投与を含めて入院は必要ありません。
使用期間は決められていません。ユルトミリス®は再発を予防する薬です。この薬を始めて病状が安定し、副作用に問題がなければ続けた方がいいといえます。
日本を含めた世界的な臨床試験では、全員にユルトミリス®が投与されました。比較対象としてソリリス®の治験の偽薬群のデータが用いられました。結果、投与開始から50週間の経過観察において、ユルトミリス®投与群では再発が認められた人はいませんでした。
「再発しない=効果が出ている」と考えると、いつから薬の効果が出ているのかは判断が難しいですが、ユルトミリス®投与後の血液中の補体の量は、治療開始1時間後には低くなることが分かっています。そのことから、ユルトミリス®は比較的早く効果が出始めるだろうと考えられています。
ユルトミリス®を使用してもNMOSDは完治しません。現在、NMOSDを完治させる薬は存在しません。
日本人ではユルトミリス®が効かない遺伝子を持っている人が約3.5%いるため、投与を受ける患者さんはそのような遺伝子があるかどうかを検査する必要があります。検査は必須とはされていませんが、この遺伝子を持っている場合はこの薬の効果が全く期待できません。患者さん側には金銭的な負担はなく、採血で分かる検査です。できる限り調べてもらうようにしてください。
一方で、ユルトミリス®の投与を急ぐ時は投与後、補体の活性化が阻害されたことを血液検査で確認する場合もあります。
ユルトミリス®の添付文書には「抗アクアポリン4抗体陽性の患者に投与すること」と記載されており、陰性の患者さんには使えません。
小児NMOSDに対しての臨床試験は行われていませんが、他の小児疾患で使われていることから、治療選択肢の1つとして検討されるかもしれません。
髄膜炎菌感染症の他、播種性淋菌感染症、肺炎球菌感染症、インフルエンザ菌感染症(細菌による感染症。ウイルスによって起こる季節性のインフルエンザとは全く異なります)など、重篤な感染症に注意が必要です。
ユルトミリス®の維持期の年間薬剤費は体重によって異なり、2024年4月1日現在、約4,547〜5,457万円です。しかしNMOSDの再発予防薬として承認されているため、指定難病の条件を満たせば医療費助成が受けられます。詳しくは「医療費助成」をご覧ください。
副作用
副作用として髄膜炎菌感染症を含む感染症、点滴に伴う全身反応(インフュージョンリアクション)などが報告されています。インフュージョンリアクションはアレルギー反応や頭痛、ショック、アナフィラキシーなどで、点滴を始めてすぐに起こることが多いです。そのため点滴終了後は一定時間、病院内での経過観察が求められます。
髄膜炎菌は重度の髄膜炎や敗血症を引き起こす細菌で、髄膜炎菌感染症はユルトミリス®の副作用の中で最も懸念される重篤な副作用です。発熱や風邪のような症状で発症した後に急激に悪化して1日で死に至ることがあります。
そのためユルトミリス®の投与を受ける場合は、治療開始2週間前までに必ず髄膜炎菌に対するワクチンを接種することになっています。ステロイド薬や免疫抑制薬などを使用している場合には、8週以上間隔を空けて2回接種することが推奨されています。
髄膜炎菌ワクチンには、4価の髄膜炎菌ワクチン (MenACWYワクチン) と血清群Bワクチン (MenBワクチン) の2種類があり、両方の接種が推奨されていますが、日本で認可されているのはMenACWYワクチンだけです。MenBワクチンは一部のトラベルクリニックなどで自費で接種できます。米国疾病対策予防センターでは「MenACWYワクチンとMenBワクチンの両方を接種しておくこと。治療中は予防的に抗菌薬を内服することを考慮すること」としています。
またワクチンはその後も5年ごとに接種することが勧められています。しかしワクチンを接種していても感染する可能性は残り、注意が必要です。実際、58人が参加したユルトミリス®の治験では、髄膜炎菌のワクチンを接種していたのにもかかわらず、2人が髄膜炎菌感染症を発症しています。高い頻度であり、特に注意が必要です。
髄膜炎菌感染症が疑われる症状は、発熱、頭痛、吐き気・嘔吐、筋肉の痛みなどです。その他、うなじのこわばり、発疹、光が異常にまぶしく感じる、手足の痛み、混乱して考えがまとまらない、などの症状にも注意が必要です。
風邪やインフルエンザと区別が付きにくいですが、これらの症状が現れたら直ちに主治医または緊急時に受診可能な医療機関に連絡してください。主治医や医療機関と連絡が取れない場合はすぐに救急車を呼び、「患者安全性カード」を救急救命室のスタッフに提示してください。
ユルトミリス®による治療中は、髄膜炎菌以外にも播種性淋菌感染症、肺炎球菌感染症、インフルエンザ菌感染症(細菌による感染症。ウイルスによって起こる季節性のインフルエンザとは全く異なる)など、他の重篤な感染症にも注意が必要です。
淋菌感染症は多くの場合は無症状ですが、排尿時の痛み、陰茎先端部からの膿様分泌物、膣分泌物の増加および腹部/骨盤部の痛みなどの症状が見られることがあります。播種性淋菌感染症が全身感染を来し、髄膜炎や心内外膜炎を合併することもあります。
風邪症状の他、原因不明の発熱や一般的な風邪とは異なる症状など、気になる症状が現れた場合は診察を受けてください。生物学的製剤で懸念される進行性多巣性白質脳症(PML)に関しては、ユルトミリス®では報告されていません。
他の治療・予防接種について
ユルトミリス®とステロイド薬・免疫抑制剤との併用は禁止されていませんが、これらの薬と併用することで、より感染症のリスクが増す可能性があります。
NMOSD患者さんの多くはステロイド薬や免疫抑制薬、そして対症療法のための薬剤を服用していますが、そういった薬剤との併用は禁止されていません。
ユルトミリス®使用中の急性増悪期の治療は禁止されていません。再発と考えられる場合にはステロイドパルス療法や血漿浄化療法が行われることがあります。次回のユルトミリス®投与については主治医と相談してください。
血漿浄化療法や、また、免疫グロブリン静注療法を行うとユルトミリス®の血中濃度が下がることが分かっています。そのため、これらの治療を行った後にはユルトミリス®の補充療法が必要となります。
ユルトミリス®から他の薬剤への変更は可能です。薬によって作用機序・投与方法・投与頻度が異なるので、変更する薬の種類や変更のタイミングは主治医とご相談ください。
ユルトミリス®の治療中でもワクチンは受けられます。ワクチンの接種時期は気にしなくて構いません。ステロイド薬や免疫抑制薬を併用していなければ生ワクチンも可能です。
日常生活
運動や仕事の制限は特にありません。
妊娠・出産
ユルトミリス®の使用経験により、妊娠・出産できなくなることはありません。添付文書には「妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること」と書かれています。妊娠中も継続するかは主治医とご相談ください。
添付文書では「治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること」とあり、患者さんそれぞれの状況と主治医の判断によるようです。
ただ、ユルトミリス®のような抗体製剤は、乳児の消化管で消化されるので、大きな影響は与えないとの見解もあります。

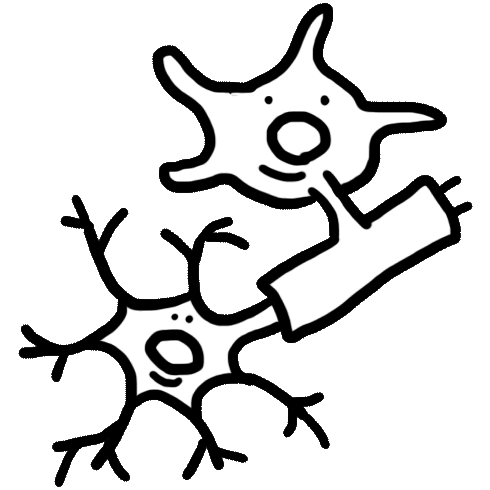
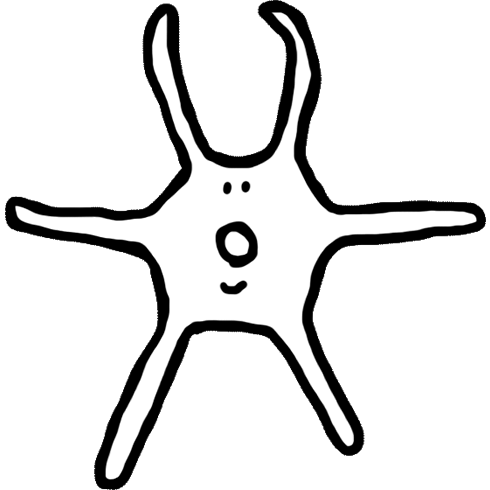
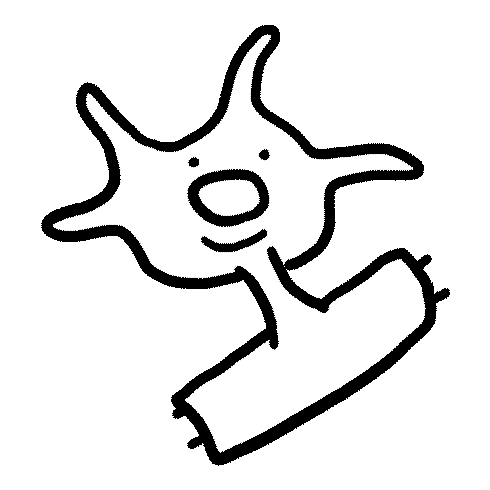
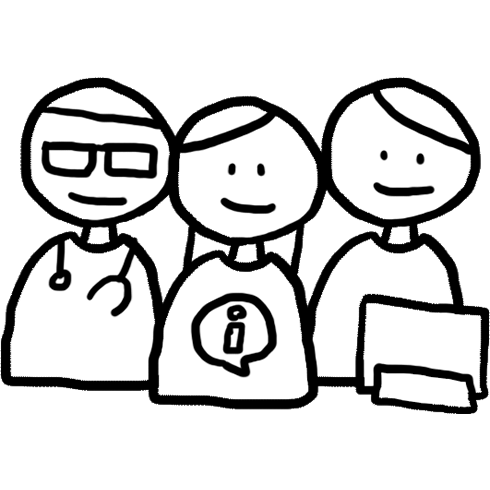
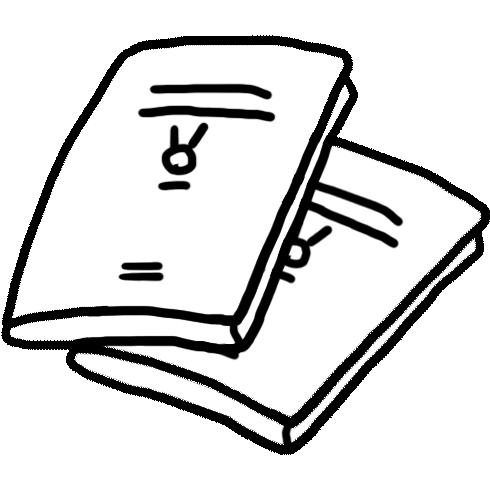
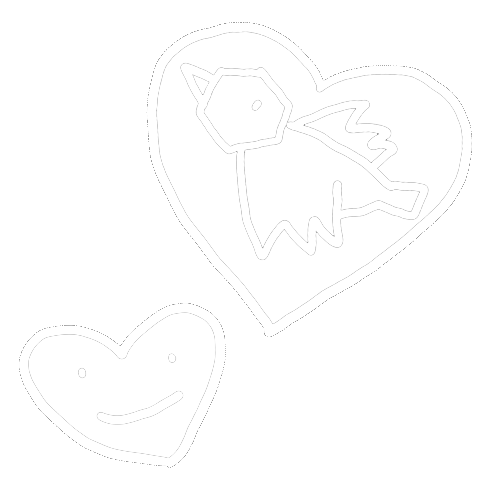
更新:
2024年3月28日(全体を改訂)
2023年9月4日(新規公開)
文:MSキャビン編集委員
大橋高志、越智博文、近藤誉之、中島一郎、新野正明、宮本勝一、横山和正、中田郷子