MSには根治療法はありません。治療は、再発した時の「急性増悪期の治療」、経過を悪化させない「再発予防・進行抑制の治療」、そして残った症状をやわらげる「対症療法」の3つに分けられます。
どの治療をどのタイミングで行うかは、個々の患者さんで違います。実際の治療は主治医とよくご相談ください。
急性増悪期の治療
急性増悪期のMSで最もよく行われるのは「メチルプレドニゾロン大量静注療法(ステロイドパルス療法)」です。通常、メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム(ソル・メドロール®)を1日に500〜1,000 mg、3〜5日間点滴します。これを「1クール」といいます。クールとは「1つの治療期間」といった意味です。
MSでは通常、ステロイドパルス療法を1クール行います。効果が不十分な時にはもう1〜2クール行うこともあります。
ステロイドパルス療法の効果が十分に得られない場合や、副作用のために大量のステロイド薬が使えない場合は、血漿浄化療法(単純血漿交換療法、二重濾過血漿分離交換療法、血漿免疫吸着療法)が行われることがあります。例えるならば腎不全で行われる透析のような治療で、血液を体の外に取り出して機械にかけた後、体に戻します。
再発予防・進行抑制の治療
MSの多くは、再発と寛解を繰り返しながら、症状が徐々に悪化する進行期に入ります。
進行期に入るまでの期間は人によりますが、病巣ができるのを抑え、症状が徐々に悪化する進行期に入らないようにしておくことが必要です。そのために使われるのが再発予防・進行抑制の薬です。経過を改善するという意味合いで「疾患修飾薬(disease-modifying drug : DMD)」と呼ばれます。そしてこの疾患修飾薬を用いることを「疾患修飾療法(disease-modifying therapy : DMT)」といいます。
日本では2024年9月現在、下記8種類のDMDが承認されています。
日本国内で承認されている疾患修飾薬 (国内承認順)
インターフェロン・ベータ1b(ベタフェロン®)→Q&Aへ
国内承認:2000年9月
使い方:皮下注射
回 数:2日に1回
副作用:インフルエンザ様症状、注射部位反応、肝機能異常、白血球数・リンパ球数減少、抑うつ、自殺企図、間質性肺炎など
インターフェロン・ベータ1a(アボネックス®)→Q&Aへ
国内承認:2006年7月
使い方:筋肉注射
回 数:1週間に1回
副作用:インフルエンザ様症状、注射部位反応、肝機能異常、白血球数・リンパ球数減少、抑うつ、自殺企図、間質性肺炎など
フィンゴリモド塩酸塩(イムセラ®、ジレニア®)→Q&Aへ
国内承認:2011年9月
使い方:飲み薬
回 数:1日1回
副作用:初回投与時の徐脈性不整脈、感染症、肝機能異常、黄斑浮腫、進行性多巣性白質脳症(PML)など
ナタリズマブ(タイサブリ®)→Q&Aへ
国内承認:2014年3月
使い方:点滴
回 数:4週に1回 ※添付文書では4週に1回となっていますが、多くの施設では6〜7週間に1回
副作用:投与時反応、過敏症、進行性多巣性白質脳症(PML)など
グラチラマー酢酸塩(コパキソン®)→Q&Aへ
国内承認:2015年9月
使い方:皮下注射
回 数:毎日
副作用:注射部位反応、注射直後反応、過敏性反応など
フマル酸ジメチル(テクフィデラ®)→Q&Aへ
国内承認:2016年12月
使い方:飲み薬
回 数:1日2回
副作用:潮紅、皮膚症状、消化器系症状、肝機能障害、白血球数・リンパ球数減少、感染症、進行性多巣性白質脳症(PML)など
シポニモドフマル酸(メーゼント®)→Q&Aへ
国内承認:2020年6月
使い方:飲み薬
回 数:1日1回
副作用:初回投与時の徐脈性不整脈、感染症、肝機能異常、黄斑浮腫、進行性多巣性白質脳症(PML)など
オファツムマブ(ケシンプタ®)→Q&Aへ
国内承認:2021年3月
使い方:皮下注射
回 数:4週に1回
副作用:潮紅、皮膚症状、消化器系症状、肝機能障害、白血球数・リンパ球数減少、感染症、類似薬でPML(進行性多巣性白質脳症)が報告
残った症状を緩和
MSでは、急性増悪期の治療を適切に行っても、症状が十分に回復せずに残ってしまうことがあります。それがこの先良くなっていくのか、または良くならないのかは分かりません。
次の症状は薬で軽減できることがあります。我慢せず、薬の服用を主治医とご相談ください。
※一部の薬を掲載しています。使われる薬は他にもあります。
痛み、しびれ
抗てんかん薬
カルバマゼピン(テグレトール®)、トピラマート(トピナ®)、クロナゼパム(リボトリール®、ランドセン®) 、フェニトイン(アレビアチン®)、ガバペンチン(ガバペン®)など
抗うつ剤
アミトリプチリン(トリプタノール®)、イミプラミン(トフラニール®)、デュロキセチン(サインバルタ®)、パロキセチン(パキシル®)、エスシタロプラム(レクサプロ®)など
その他
プレガバリン(リリカ®)、ミロガバリン(タリージェ®)、トラマドール/アセトアミノフェン(トラムセット配合錠®)、メキシレチン(メキシチール®)など
つっぱり
バクロフェン(リオレサール®、ギャバロン®)、チザニジン(テルネリン®)、ガバペンチン(ガバペン®)、ジアゼパム(セルシン®、ホリゾン®)、ダントロレン(ダントリウム®)など
疲 労
アマンタジン(シンメトレル®)、レボカルニチン(エルカルチン®)、補中益気湯など
排尿障害
膀胱の筋肉が過敏に反応してしまう場合
ビベグロン(ベオーバ®)、ミラベグロン (ベタニス®)、イミダフェナシン (ウリトス®、ステーブラ®)、フェソテロジン (トビエース®)、オキシブチニン(ポラキス®)、フラボキサート(ブラダロン®)、プロピベリン(バップフォー®)、トルテロジン(デトルシトール®)、プロパンテリン(プロ・バンサイン®)、ソリフェナシン(ベシケア®)など
排尿時に尿道の筋肉が緩まない場合
ウラピジル(エブランチル®)、ナフトピジル (フリバス®)、タムスロシン(ハルナール®)など
筋肉の収縮が弱い場合
ベタネコール(ベサコリン®)、ジスチグミン(ウブレチド®)など
排便障害
便秘(便を柔らかくする)
酸化マグネシウム(酸化マグネシウム®、マグミット®、マグラックス®)、クエン酸マグネシウム(マグコロール®)、ルビプロストン (アミティーザ®)、リナクロチド (リンゼス®)、エロビキシバット (グーフィス®)、マクロゴール4000・ポリエチレングリコール4000 (モビコール®)、潤腸湯、大建中湯、麻子仁丸など
便秘(腸を刺激する)
センノシド(プルゼニド®)、センナ(センナ®、アローゼン®)、ピコスルファートナトリウム(ラキソベロン錠®、ラキソベロン内容液®)、ビサコジル(テレミンソフト坐薬®)など
便失禁
下痢止めのロペラミド(ロペミン®)、便の固さを調整するポリカルボフィルカルシウム(ポリフル®)などがあります。便が緩くて困る場合はビフィズス菌製剤(ラックビー®)や酪酸菌製剤(ミヤBM®)など
多発性硬化症の治療(15分半)
富沢雄二 先生(順天堂大学)
(2024/9/3更新)

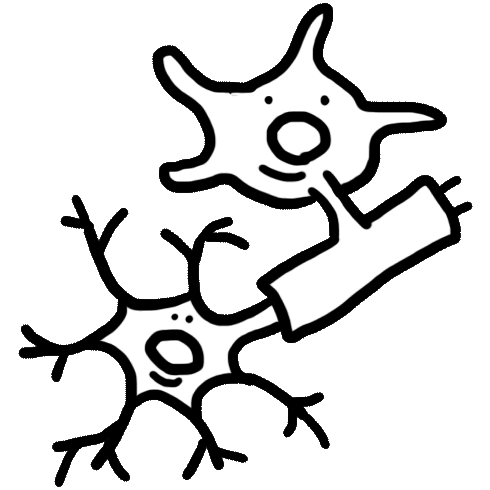
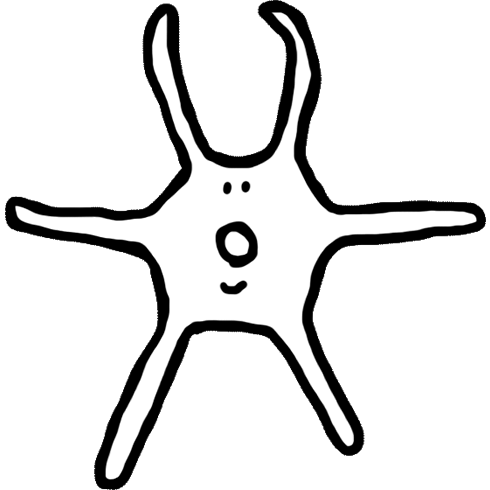
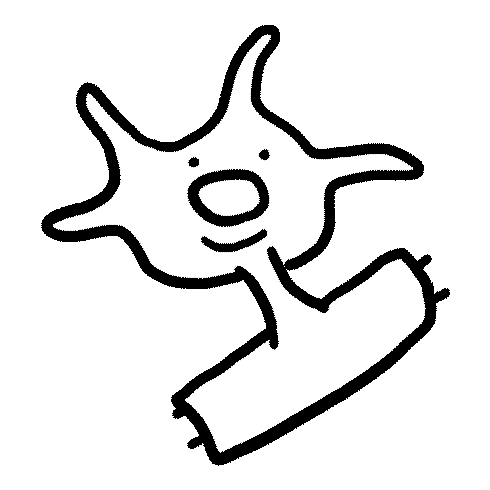
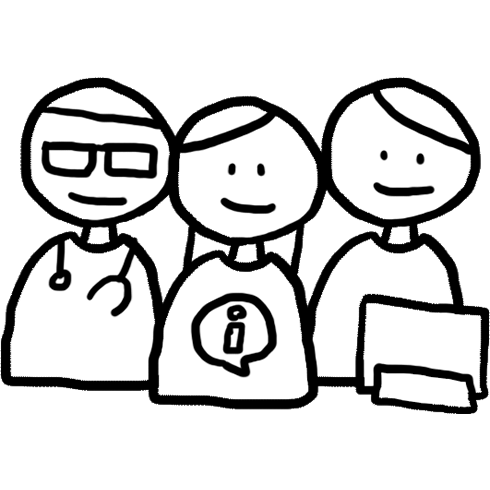
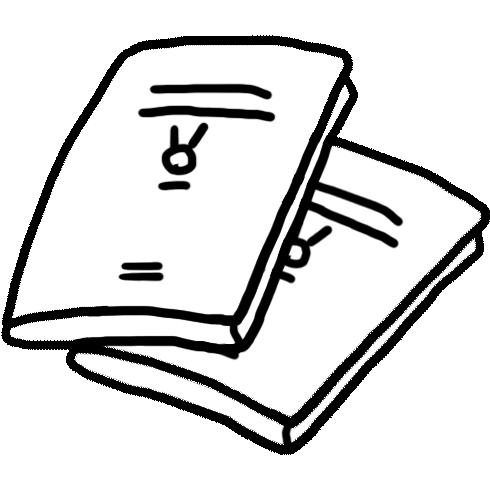
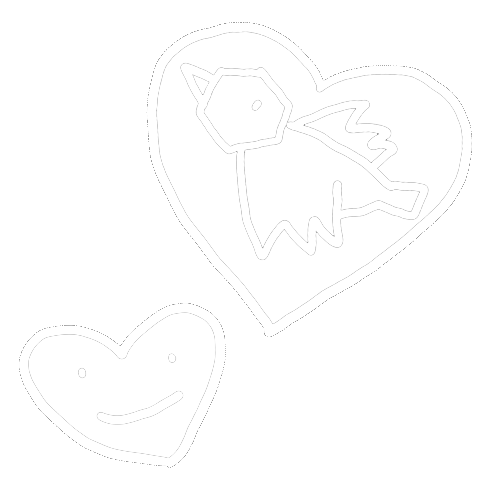
「多発性硬化症と視神経脊髄炎の疼痛」
近藤誉之 先生(関西医科大学総合医療センター)